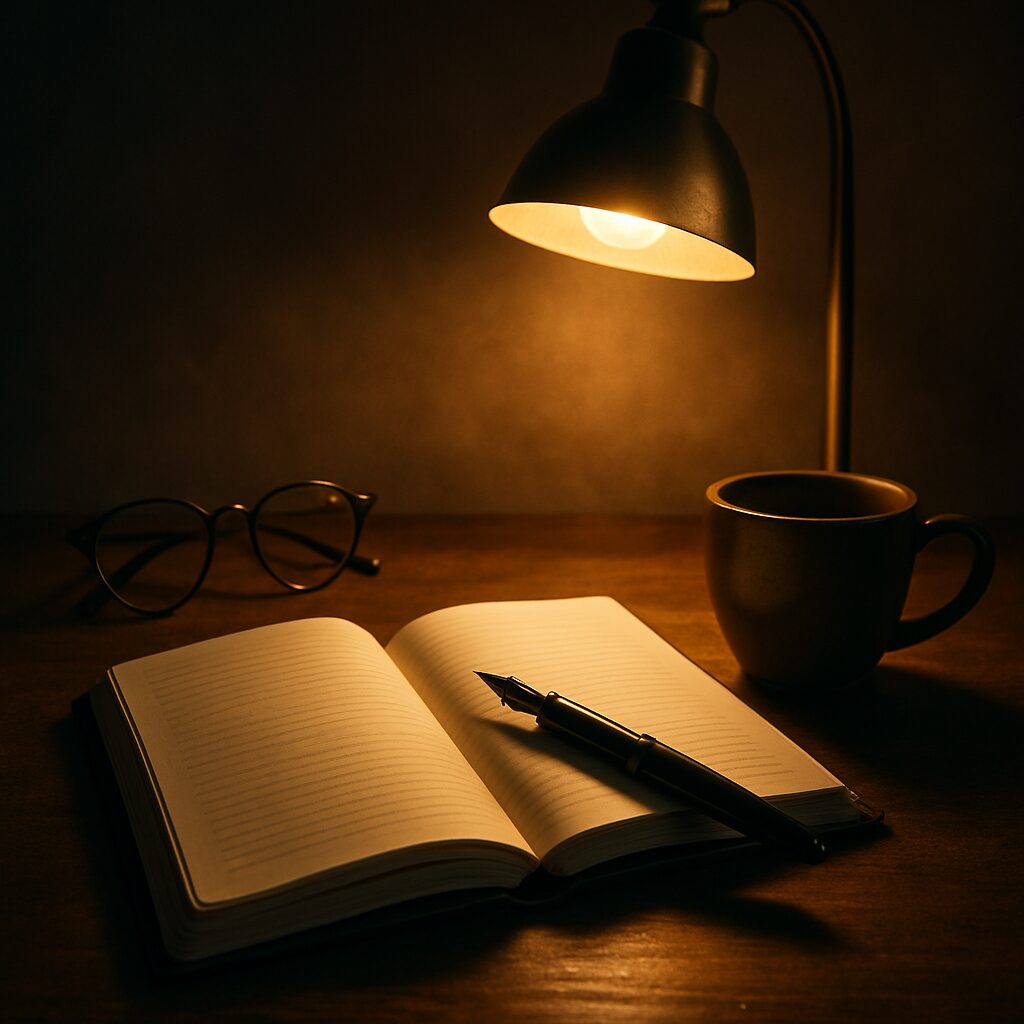こんにちは。今回は「お城好きライター」のやまもとますみが担当いたします。
お城めぐりが趣味で、休日には各地のお城や城跡を訪ね歩くのが私の楽しみのひとつです。石垣を見たり、櫓に登ったり、歴史に思いを馳せる時間は本当に心を満たしてくれます。その中で、私がいま一番行ってみたいと強く感じている場所があります。それは長野県上田市にある「上田城」です。名前を耳にするだけで胸が高鳴るようなお城で、戦国時代ファンにはおなじみの真田一族ゆかりの名城として知られています。
2016年のNHK大河ドラマ『真田丸』が放送された際には、その舞台となったことで一気に注目度が高まり、放送当時は連日多くの観光客や歴史ファンで賑わいました。真田丸をきっかけにお城に興味を持った方も多かったのではないでしょうか。そして驚くべきことに、過去に「お城ファンが選んだ好きな城ベスト10」で堂々の第1位に輝いた実績まであるのです。あの世界遺産である姫路城や、日本三名城のひとつ大阪城をおさえての第1位というのは、本当に快挙だと思います。
お城好きとしては、国宝や世界遺産と肩を並べ、時にそれ以上に愛される上田城の魅力を知るだけで胸が熱くなります。私自身も大河ドラマを通じて歴史の舞台としての上田城に深く惹かれましたし、ファンランキングで支持されている姿に触れるとますます気持ちが高まり、今すぐにでも訪れてみたいという思いが強くなります。
上田城の基本データ
- 名称:上田城(うえだじょう)
- 所在地:長野県上田市二の丸
- 築城年:1583年(天正11年)
- 築城主:真田昌幸
- 歴代城主:真田氏・仙石氏・松平氏
- 現存する櫓:南櫓・北櫓・西櫓(いずれも長野県宝に指定)
- 日本100名城(27番)に選定
- 城の形式:平城(千曲川を利用した自然の要害を備える)
- 特徴:石垣の野面積みや、土塁・堀の痕跡が残り、戦国期の築城術を知る貴重な遺構
明治7年(1874年)に廃城令により取り壊されましたが、現在は「上田城跡公園」として市民に親しまれています。桜の名所でもあり、お花見シーズンにはたくさんの人で賑わうのだとか。園内には博物館や真田神社もあり、歴史を感じながら散策できる環境が整えられています。また、春の桜だけでなく、秋には紅葉も見事で、四季を通じて楽しめる観光スポットとなっています。
天守は存在した?ロマンを呼ぶ議論
お城好きとして気になるのが「天守はあったのか?」という点です。古い記録には「天守も無き小城」と書かれている一方で、近隣の松本城や小諸城には天守があるため、建てられていた可能性を指摘する声もあります。さらに、真田昌幸の嫡男である信幸が居城とした沼田城には天守が存在していたことから、上田城にも同様の構造物が計画されていたのでは、と推測する研究者もいるのです。
一方で、天守台らしき石垣が確認されていないことや、当時の経済力を考えると天守を築く余力がなかったのではという説も根強くあります。そのため「幻の天守」という表現で語られることも多いのです。現地を訪れると、もしここに天守が建っていたらどのような姿だったのだろう、と想像が膨らみます。はっきりとした資料は見つかっていませんが、「あったのでは?」と想像するだけで心が躍るのは私だけではないはず。こうした歴史の余白を楽しみ、事実と推測を行き来しながら歩くことこそ、お城めぐりの大きな醍醐味ですよね。
上田城と真田の戦い
やはり上田城といえば「上田合戦」を語らずにはいられません。歴史書や小説、大河ドラマなどで幾度となく取り上げられてきた戦いであり、真田一族の知略を象徴する場面でもあります。
1585年、築城からわずか2年後に起きた第一次上田合戦。
徳川軍7000人に対し、真田軍はわずか2000人。圧倒的に不利な状況でしたが、地形を生かし、奇策を駆使して徳川軍を撃退しました。川を利用した戦術や、城下に仕掛けられたトリックなどが功を奏し、少数精鋭が大軍に立ち向かう姿は日本人の心を大いに揺さぶります。この合戦で真田家の名は一気に全国に知れ渡り、独立した大名としての立場を確立していくことになりました。
さらに1600年には第二次上田合戦。関ヶ原の戦いと同じ年に起こったこの戦いは、歴史の転換点として特に有名です。徳川秀忠率いる3万8000人に、真田昌幸・幸村(信繁)はまたも2000人で対抗しました。籠城戦においては城内外の連携や奇襲が繰り返され、徳川軍は思うように進軍できず、ついには関ヶ原の本戦に遅刻してしまうという大失態につながります。3万8000人の兵力が本戦に参加できなかったことは、戦局にも大きな影響を与えたと考えられています。
私はこのエピソードを読むたびに胸がすっとするのです。数で勝る相手に堂々と立ち向かい、知略で勝ち抜く――これぞ真田の強さと誇りだと感じます。勝敗そのものだけでなく、時代に残した影響やその後の戦国史に刻まれた意味を思うと、上田城の戦いはまさに日本史におけるドラマのひとつだと言えるでしょう。
その後の上田城
合戦のたびに徹底的に破壊され、堀も埋められた上田城。しかしその後、地域の人々の手で整備され、今は美しい歴史公園として姿を変えています。園内には真田神社や博物館が設けられ、歴史を学びながら散策できるようになっており、市民の憩いの場としても愛されています。桜や新緑、紅葉など四季折々の風景のなかでお城を感じられるのは、とても贅沢な体験で、春はお花見、秋は紅葉狩りと、訪れる季節ごとに違った魅力を楽しめます。冬の雪化粧をまとった姿もまた格別で、写真映えする景観として人気があります。
また、真田一族の複雑な運命、兄の信幸が徳川に仕え、弟の幸村は大阪の陣で最後まで戦うという歴史も、上田城を語るうえで欠かせないポイントです。なぜ兄は許され、所領を守ることができたのか。その背景には徳川家との縁組や信幸の賢明な立ち回りがあったとされますが、詳細は謎の部分も多く残されています。この謎めいた歴史の断片こそが、上田城を訪れる人の想像力を刺激し、より深い魅力を感じさせてくれるのだと思います。
まとめ:お城好きの視点から
上田城は、単なる観光スポット以上に「知恵と誇りの象徴」として私の心を掴んでいます。真田一族の歴史や合戦の記憶を宿す場所であり、訪れる人に戦国の息吹を今に伝える貴重な遺産だと感じます。もし訪れるなら、ぜひ上田城跡公園の桜や櫓を眺めながら、真田昌幸や幸村が守った戦いに思いを馳せてみてください。春は桜が一面を彩り、夏は新緑がまぶしく、秋は紅葉が堀を赤く染め、冬は雪景色が静かな美しさを与えてくれます。どの季節に訪れても、それぞれに異なる魅力があり、お城散策をいっそう特別な時間にしてくれるでしょう。お城を歩きながら「ここに天守はあったのかな?」と想像する時間もきっと特別なものになるはずです。さらに、城内の真田神社で参拝したり、資料館で歴史を学んだりすることで、ただ観光するだけでなく物語に深く触れられる体験となります。
お城好きとしても、歴史ファンとしても、上田城は「必ず訪れたい場所」のひとつ。私の夢も近いうちに叶えたいと思っています。訪れた際には、自分の目で石垣の力強さを確かめ、真田の知略が息づく舞台を存分に味わいたいです。