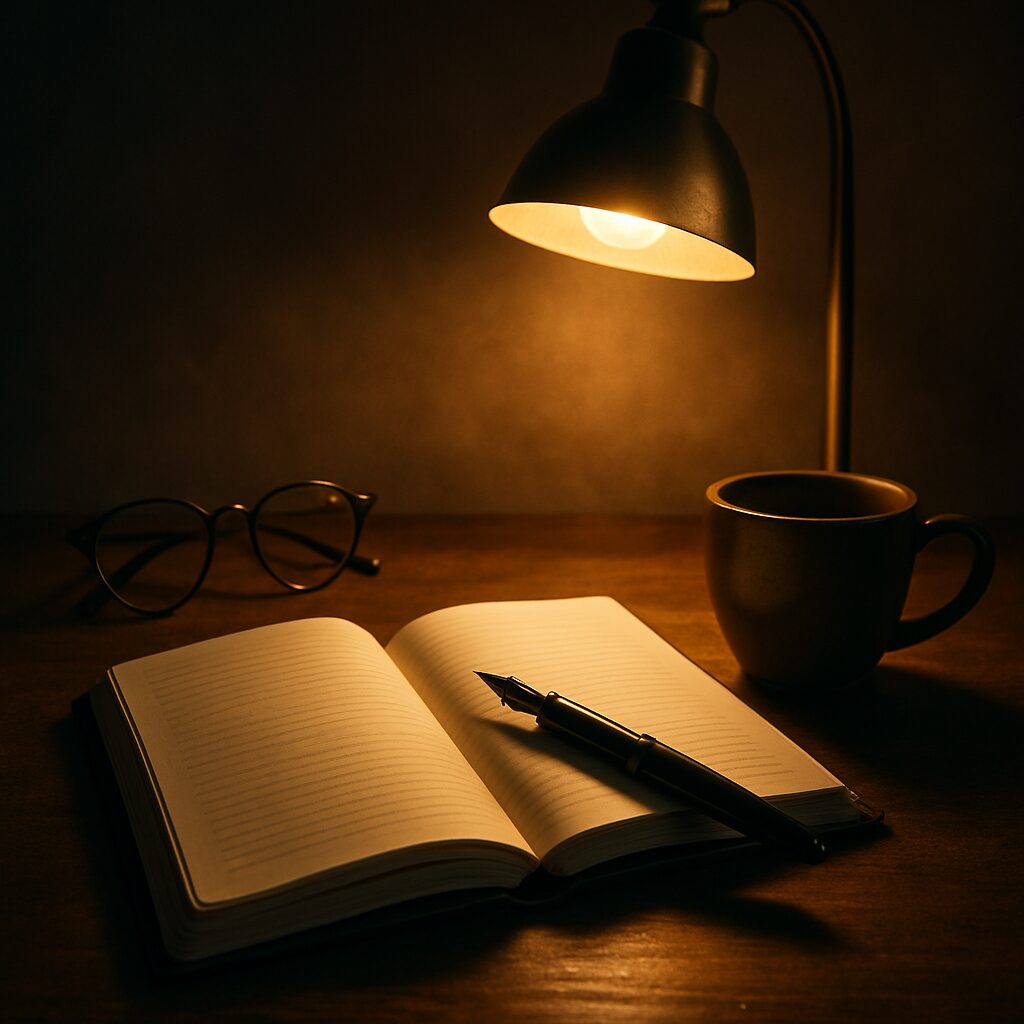こんにちは、Afterwordsの映画をこよなく愛する男「TAKAHIRO」です。今日ご紹介する映画は、辞書づくりに情熱を注いだ人々の姿を描いた名作『舟を編む』。静かな作品でありながら心に熱を与えてくれる一本です。
熱い思いが伝わる辞書編集部の姿
松田龍平さん演じる馬締光也をはじめ、辞書編集部のスタッフたちは、とにかく情熱的です。最初は気乗りしない様子で集まった人たちも、気づけば辞書づくりに夢中になり、面倒で膨大な作業にのめり込んでいく。その年月はなんと15年にも及びます。特に印象的だったのは、辞書編纂が佳境を迎えた時に「単語の欠落」が発覚する場面。すべての作業を中断し、改めて欠落がないかを徹底的に確認することになります。その際、馬締が学生アルバイトに泊まり込みを頼むと、最初は「さすがに無理では…」という空気が流れます。しかし、ひとり、またひとりと「やります」と声を上げ、最終的には「ここまで来たら最後までやり切ろう」という熱気に包まれるのです。
なぜ人は熱くなれるのか?
辞書編纂という仕事そのものが人を熱くさせるわけではありません。本質的な理由は「一冊を完成させたい」という強い思いにあります。妥協を許さない姿勢が、スタッフ全員を突き動かしているように感じました。
オダギリジョーさん演じる西岡も、最初はどこか他人事のように辞書づくりに向き合っていました。しかし馬締の誠実な姿勢に触れるうちに、仕事への愛着を持ち、情熱的に取り組むように変わっていきます。黒木華さん演じる岸部も同様で、最初は引き気味だったのに、いつの間にか辞書に人生をかけるようになっていました。
「なぜ人は熱くなるのか?」という問いの答えが、ここに集約されている気がします。
自分の仕事にも通じる「コツコツの大切さ」
映画を観ながら強く感じたのは、辞書編纂の姿勢は日常の仕事にも通じるということです。15年という膨大な時間をかけ、ひとつのものを完成させる。その過程には困難や停滞もあるでしょうが、それでも積み重ねていくことが大切なのだと改めて気づかされました。
「コツコツと続ける」という地道な作業が、やがて大きな成果へとつながっていく。この映画を観て、自分の仕事も投げ出さず取り組んでいこうという気持ちになりました。
印象に残ったキャラクターたち
馬締光也という人物像
松田龍平さん演じる馬締は、序盤こそ不器用で強烈なキャラクターに映ります。しかし物語が進むにつれ、彼の人間性の深さと誠実さが際立ち、気づけば「カッコいい人物」へと変わっていくのです。その変化は急激ではなく、じわじわと積み重なる小さな行動や姿勢から生まれており、観客は彼の内面に宿る誠実さに自然と惹きつけられていきます。例えば、仲間に対する言葉の選び方や、困難に直面したときに見せる真摯なまなざし、そして決して派手ではないが確実に周囲を動かす行動力。そうした一つ一つが彼を特別な存在へと押し上げています。見かけの格好良さではなく、人としての在り方に心を打たれ、最後には「こうありたい」と思わせるような憧れを抱かせるキャラクターでした。
香具矢の魅力
宮﨑あおいさん演じる香具矢も忘れがたい存在です。彼女の登場シーンはどれも印象的で、ひとつひとつが馬締との関係を深めていく大切な場面となっています。下宿先の台所で包丁を研ぐ後ろ姿、その「うなじ」の美しさに見とれる馬締の視線は、観ているこちらまで引き込まれるほどで、日常の何気ない所作がこんなにも輝いて見えるのかと驚かされました。さらに、玄関先での告白シーンも心に残ります。「好きです」と伝える馬締に対して、少し驚きながらも穏やかに「私も」と応える香具矢。その瞬間の素直さと温かさには、胸が高鳴ると同時に、二人がこれから築いていく人生への確かな一歩を感じさせます。また、香具矢は単なるヒロインではなく、馬締の誠実さに触れながら自らも成長していく存在として描かれている点が魅力的です。料理人としての真剣な姿や、周囲を自然と和ませる柔らかい雰囲気は、作品全体に温度を与えています。観客にとっても、彼女の姿は「人を支えることの美しさ」を実感させるものであり、その存在感は物語をより豊かにしていました。
西岡と岸部の変化
西岡や岸部といった周囲の人物も、馬締の姿に感化されて少しずつ変わっていきます。最初は自分の仕事を事務的にこなすだけで、辞書づくりに強い意味を見いだせなかった彼らも、馬締が見せる真剣さや、言葉ひとつひとつに向き合う姿勢に触れることで、次第に心を動かされていきました。例えば西岡は、当初は軽い気持ちで編集部に関わっていたのに、馬締の誠実な働きぶりに影響され、次第に「自分もこの辞書に関わっている」という自負を持ち始めます。岸部もまた、最初は周囲の熱量に戸惑い距離を置いていたのに、日々の積み重ねの中で徐々に意識が変わり、やがては仲間の一員として情熱的に取り組むようになっていくのです。やる気のなかった人間が本気になり、情熱を持って行動する姿は、人が人を動かす力を象徴していました。それは単なる仕事上の変化ではなく、人間関係の中で自然と伝播する「熱」が、個々の内面に火を灯していった結果なのだと感じられました。
映画の見どころと余韻
15年かけて完成した「大渡海」
辞書「大渡海」が完成した瞬間の喜びは、言葉に尽くせないほど大きなものでした。完成記念のパーティーに立つ馬締の姿は、観る者に「やり切ることの美しさ」と同時に、長い年月の努力が実を結ぶ瞬間の尊さを強く印象づけます。長い時間を支え合った仲間たちの笑顔や涙がそこにあり、15年という途方もない時間の重みが一層心に響いてきます。
ただ同時に、「燃え尽き症候群にならないか」という不安もよぎります。しかし、馬締はすでに新しい言葉のストックを抱えており、翌日から改訂作業に入ると言います。その言葉を聞いた時、観客は彼の情熱が一過性のものではなく、生涯を通して言葉と向き合う覚悟であることを理解します。その姿には、言葉への果てしない情熱と、未来に向けたたゆまぬ挑戦の気配を強く感じさせられました。
地味なのに熱い、不思議な感動
辞書づくりは決して派手な仕事ではありません。むしろ毎日地道で忍耐を要する作業の積み重ねです。けれど、その先にある達成感や仲間との結束が、想像以上に心を揺さぶります。観終えた後には、静かな感動と共に「自分も頑張ろう」と自然に思える、不思議な力をもらえる作品でした。そしてその余韻は、映画を見終えた後もしばらく胸の奥に残り、日々の生活を前向きにする小さな原動力となってくれるのです。
映画情報:『舟を編む』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品名 | 舟を編む |
| 公開年 | 2013年 |
| 監督 | 石井裕也 |
| 原作 | 三浦しをん『舟を編む』(2011年、光文社) |
| 上映時間 | 133分 |
| 主演 | 松田龍平、宮﨑あおい |
| 共演 | オダギリジョー、黒木華、小林薫 ほか |
| 受賞歴 | 第37回日本アカデミー賞 最優秀作品賞・最優秀監督賞 ほか多数 |
| 備考 | 第86回アカデミー賞(外国語映画賞)日本代表作品 |
主演・松田龍平さんについて
本作の主人公・馬締光也を演じた松田龍平さんは、独特の存在感を放つ俳優として知られています。
プロフィール
- 生年月日:1983年5月9日(東京都出身)
- 身長:183cm
- 血液型:B型
- 父は俳優の松田優作さん、母は女優の松田美由紀さん。弟は松田翔太さん。
学生時代に北野武監督からスカウトを受け、映画『御法度』(1999年)で俳優デビュー。同作で日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞し、一躍注目を集めました。
主な出演作品
- 映画
- 『御法度』(1999年)
- 『青い春』(2001年)
- 『恋の門』(2004年)
- 『まほろ駅前多田便利軒』(2011年)
- 『舟を編む』(2013年)
- 『泣き虫しょったんの奇跡』(2018年)
- 『影裏』(2020年)
- ドラマ
- 『あまちゃん』(2013年/NHK)
- 『カルテット』(2017年/TBS)
- 『大豆田とわ子と三人の元夫』(2021年/フジテレビ系)
松田龍平さんは、派手な演技ではなく「静かな情熱」や「人間の奥行き」を表現することに長けた俳優です。本作『舟を編む』でも、寡黙ながらも誠実に辞書づくりへ向き合う馬締光也を見事に体現し、その存在感が物語全体を支えています。
簡単なあらすじ
玄武書房が「大渡海」という辞書の編纂を決定します。定年を間近に控えた編集者・荒木(小林薫)は、次世代を担う人材として馬締光也に声をかけ、彼を辞書編集部へと導きます。馬締は言葉に対する鋭い感性と真摯な姿勢を持ちながらも、当初は人付き合いが苦手で周囲に溶け込めない存在でした。しかし、その誠実さが徐々に仲間の信頼を集めていくのです。同僚の西岡(オダギリジョー)やベテランの荒木らと共に作業を進める中、編纂中止の圧力や人事異動など、数々の困難が立ちはだかります。資金不足や社内の理解不足といった現実的な壁もあり、プロジェクトは幾度となく危機を迎えました。それでも馬締は言葉への情熱を失わず、仲間たちもその姿に鼓舞されながら辞書づくりに打ち込みます。その過程で馬締は下宿先「早雲荘」で香具矢(宮﨑あおい)と出会い、やがて恋に落ちます。香具矢は料理人を目指す芯の強い女性であり、馬締の誠実さに心を開き、二人は結婚へと至ります。仕事だけでなく人生の伴侶を得た馬締は、さらに大きな支えを得て困難を乗り越えていくことになります。15年という長い歳月を経て、ついに辞書「大渡海」は完成します。しかし監修者である松本朋佑先生の死により、その完成を直接見届けてもらうことは叶いませんでした。それでも仲間たちの努力は確かな形となり、辞書は後世に残る大きな仕事として結実したのです。
まとめ|「舟を編む」が教えてくれること
『舟を編む』は、辞書という一見地味な題材を扱いながらも、人が何かに情熱を注ぐ姿の美しさを鮮やかに描いた作品です。馬締光也をはじめとする登場人物たちは、それぞれのきっかけや思惑を超えて「一冊の辞書を完成させる」という目標に心をひとつにしていきます。その姿には、仕事や人生に向き合う私たちへの大きなヒントが込められていると感じました。15年という長い年月をかけ、途方もない作業を積み重ねる姿は、地味でありながら確かに胸を打ちます。「情熱は対象そのものではなく、作り上げたいという強い思いから生まれる」この映画を通じて改めて学ぶことができました。
自分の仕事や日常の中で、もし気持ちが停滞している人がいるなら、この映画はきっと心に火を灯してくれるはずです。静かで誠実、しかし確かな熱さを秘めた一本。『舟を編む』は、観終えた後にじんわりと勇気を与えてくれる映画だと思います。